コオロギの外骨格における色と硬さの関係
濃い色は硬く、薄い色は柔らかい?
昆虫の外骨格(クチクラ)の色と硬さには密接な関係があります。一般的に、外骨格が黒っぽく色が濃い部分は硬く丈夫で、淡い色の部分は柔らかく弾力性があります[1]。これは外骨格のスケレチン化(タンニング, sclerotization)という過程によるものです。スケレチン化とは脱皮直後の柔らかいクチクラが硬化して丈夫になる現象で、この硬化の際にクチクラが暗色化(褐色~黒色化)することが多いのです[2]。
昆虫のクチクラ硬化はキチン質とクチクラタンパク質の架橋によって起こり、この反応にはフェノール酸化酵素によるタンパク質の結合とメラニン色素の沈着が関与します[3][4]。メラニン合成経路の副産物がクチクラの硬化に寄与しており、メラニンによる着色と硬化は表裏一体の現象です[5]。
脱皮直後は白く柔らかい
コオロギが脱皮した直後の外骨格は白っぽく透き通るほど色が薄く、非常に柔らかい状態です[6]。その後数時間で外骨格のスケレチン化が進行し、次第に暗色化しながら硬さも増していきます[7]。つまり、脱皮直後の淡い色のクチクラは柔軟で、時間経過とともに濃い色へと変わりながら硬くなるのです。
色と硬さの相関関係と例外
この法則は同一個体の発育段階や体の部位を比較する場合に顕著です。しかし種が異なる場合、色と硬さの相関は必ずしも一致しません。たとえばゴミムシダマシ科の甲虫では、幼虫の黒い顎は非常に硬い一方、成虫の顎はマンガンを含んでいても比較的柔らかいという例があります[1][5]。
さらに、寒冷地の昆虫はメラニン色素を増やして体色が暗くなる傾向がありますが、この際にクチクラも厚く硬化しやすいという報告があります。これも暗色化と硬化の同時進行を示す例です。
結論
昆虫の外骨格について「色が濃い方が硬く、薄い方が柔らかい」と言えるかという問いに対しては、限定付きで「はい」と言えます。同一個体の発育過程や同種内の比較では、クチクラの色と硬さは密接に関係しています[6][7]。ただし、種間比較では他の要素が影響するため注意が必要です。全体として、暗色化とクチクラの硬化は化学的にも機能的にも強く結びついており、「濃い色=硬い」「淡い色=柔らかい」という経験則は広く当てはまる傾向にあります[5]。
参考文献
- Hardness in arthropod exoskeletons in the absence of transition metals
- Model reactions for insect cuticle sclerotization
- Melanin and sclerotization pathways in insect cuticle hardening
- Laccase-mediated cuticle sclerotization and pigmentation
- Biomechanical properties of cuticle pigmentation and hardening
- 付録 マメ知識 コオロギの生態 – フューチャーノート
- Post-molt cuticle tanning in crickets

日本の先進的なコオロギ研究を一般に紹介した最新の専門書。

高タンパク質で注目されるコオロギ食を解説した一冊。

コオロギを題材に昆虫の生態と進化を考察した古典的名著。
関連記事
 " data-srcset="'https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2023/09/F28A77F3-9864-493C-B21C-6611D059CD2D_1_201_a-1-185x400.jpeg 150w, https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2023/09/F28A77F3-9864-493C-B21C-6611D059CD2D_1_201_a-1-185x400.jpeg 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px"/>
" data-srcset="'https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2023/09/F28A77F3-9864-493C-B21C-6611D059CD2D_1_201_a-1-185x400.jpeg 150w, https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2023/09/F28A77F3-9864-493C-B21C-6611D059CD2D_1_201_a-1-185x400.jpeg 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px"/>
 " data-srcset="'https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2023/12/download.png 150w, https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2023/12/download.png 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px"/>
" data-srcset="'https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2023/12/download.png 150w, https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2023/12/download.png 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px"/>
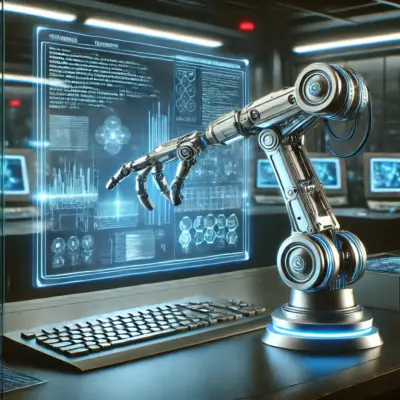 " data-srcset="'https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2025/02/jidouimo-400x400.webp 150w, https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2025/02/jidouimo-400x400.webp 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px"/>
" data-srcset="'https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2025/02/jidouimo-400x400.webp 150w, https://ubun2m.com/wp-content/uploads/2025/02/jidouimo-400x400.webp 720w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px"/>